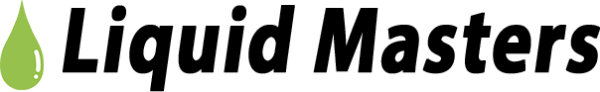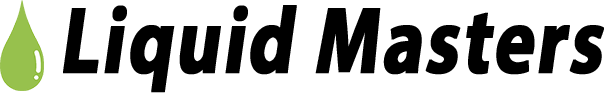ワイン用のブドウを作るまでに畑で起こりえる驚異を解説していきます。
・自然由来
・外敵(虫や動物)由来
・病気由来
のパートに分けて、それぞれの脅威と対策法も簡単に解説していきます。このページは【自然災害編】です。読み終われば少しだけブドウ畑がなんであの形なのか!が少し理解進むと思います。
他のパートはこれから書き進めます!
自然由来の脅威
ワインのブドウ畑に遅いかかる脅威は沢山あります。原因になる元は当たり前ではありますが、「温度」「水」「光」と植物の成長サイクルにかかわる物がほとんどです。
これらとその他の物も加えて順番に解説します。
温度による脅威
温度による脅威は簡単です。極端に暑いか極端に寒いのが原因だからですね。圧倒的に出やすい被害は「霜」なのでそこの解説が圧倒的に厚いのでご覧ください。
極端に暑い
極端に暑い場合と言うのは、日中の温度が40℃を超えてしまうような時です。そこまで行くとブドウは持ちこたえられません。大体、垣根仕立てのブドウ畑の場合はブドウの位置が低いですからね。
40℃超えて、太陽光がギラギラして地面が暖められたら、ブドウ付近の温度は40℃よりも上昇しますし、2019年にヨーロッパを襲った熱波なんて43℃まで上がりましたから、ブドウ付近は50℃超えたところもあると思います。普通に低温調理ですからね・・・当然枯れます。
極端に寒い
極端に寒いケースは2つあります。まず最初の一つは
・真冬に-20℃以下になる
-20℃以下に気温が落ちると、ブドウの樹は枯れてしまいます!寒すぎると越冬出来ないんですね。しかし、それ以下になる地域にも多少ブドウ畑はあります。そんな地域の予防策は、「ブドウ畑を土に埋める!」があります。
ヨーロッパではせいぜい根元に土をかぶせるぐらいですが、実際に中国に真冬全埋めする所があるそうです。真冬に「ブドウ畑見せてよ」なんて尋ねると野原らしいですよ。
・霜による被害
寒さの被害で圧倒的に脅威なのは春の遅霜です。霜は英語で「Frost」です。
これは、ブドウ畑が新芽を出す北半球なら3-4月ぐらいの問題ですが、ピンポイントで気温がやたら低下する日に置きます。日本で言うところの「桜咲いてるのに雪降っちゃう日」が来るのと一緒です。
この時、すでにブドウから新芽が出ていると、氷点下に落ち込んだ気温で、ブドウの新芽が凍結してしまうわけです。

凍結した新芽は枯れてしまいます。冷凍庫に野菜入れるとべちょべちょになるのと同じ原理です。細胞壁が壊れちゃうんですね。
新芽が死んだブドウは、次にも芽は出しますが、「最初の芽しか実を付けない」のがブドウです。理由はちゃんとあるのですが、超上級編ぐらいの解説になるので、新芽が死んだら次の芽には実がつかないだけ覚えてください!
この霜対策は結構深刻な所が多いので、いろいろな対処が考えられています
・焚火
もう気温が下がるのを防げばいいわけですからね。焚火ですよ!
ロウとかを燃やすらしいですね。ちなみに1ha辺りの費用が100万円ぐらいかかるって、生産者から聞いた事があります。「だからうちはやらない!」って言ってましたね。

でも結構やる人多いので、なんだかお祭りみたいな雰囲気になっちゃいます。キレイですよね。
実際にTwitterとかで見た問題ですが、ブドウ畑の近くの住人が「煙い!あの焚火どうにかしろ!」ってキレてるツイートを見かけたので、ブドウ畑以外の事も考えなきゃいかんなと言うのも感じはしましたね。
・水を撒く
凍っちゃうのが困るのに、水まくの?が結構大きな疑問になると思いますが、巻きまくるんです。
スプリンクラー使ってずーっと放水していると、スプリンクラーぐらいですからね、表面はしっとり濡れる。そしたらその水自体が気温の低下と共に凍ります。
新芽の表面の水も氷ります。すると新芽は氷の中です。氷の中は何気に0度以下にならない・・・そうかまくら現象です!かまくら作ると中は意外と温かいので、それでブドウの新芽自体は凍結しない作戦ですね。意外と有効です。
・ファンとかヘリコプター
様は、ブドウの新芽付近が氷点下にならなきゃいいわけです!冷たい空気って重たいから下にたまるって習いましたよね?なので一番底が冷えてるんで、その空気をかき混ぜてやろう!って作戦です。
元々霜が多い地域は送風機がついていて、それで空気をかき混ぜます。日本でもお茶畑でよく見られますよ。
元々のファンがついていないところでは、夜中中ヘリコプターを飛ばす作戦もあります。まぁ、でっかいファンですよね。
ただし、ヘリコプターはとんでもないお値段なので、相当のお金持ちしか使えない作戦です。近年ではピュリニー・モンラッシェのルフレーヴが実践してますね。
・電熱線ワイヤー
これもお金がかかる方法ですが、もともと霜が来やすい地域では導入されている所があります。
ブドウ畑に仕立てように張ってるワイヤーが電熱線で、スイッチオンすれがヒーターになる優れものです。その熱で凍るのを防ぐわけですね。
・畑をわけておく
畑単位でワインの格が決まるようなところでは出来ませんが、そうでない地域はあらかじめ、いくつかの場所に畑を分散しておく方法です。
霜って結構ピンポイントで襲ってくる事もあるので、数キロ離しておくだけで被害がなかったりもします。
光による被害

光による被害は、要するに太陽ですね。
基本的にお日様は照ってくれないと困ります!光合成しないと植物は成長に必要な「グルコース」を作れません。なので日照不足による被害が当然あります。
日照不足による被害
光合成が出来ないと起こる問題は、そもそもの生育不良が当然おきます。
光合成しないと植物の成長に欠かせない「グルコース」が作られませんので、植物が成長できないんですね。グルコースは糖分の元でもありますから、糖度も上がってくれなくなるからワインづくりには非常に困ります。
もう1つ、開花時にも問題があって、開花の時期に天候が良くないと、受粉率に大きな差が出るそうです。雨は当然物理的にも花粉が落ちちゃいそうで、受粉率低下が赤りますが、気温が低くて曇っていてもだめだそうです。
ホルモンが分泌されないとかで、受粉率が低下するそうです。開かなんてわずか数日なのでその期間のお天気は運任せ!な毎年ドキドキの瞬間です。
日照不足対策はブドウの畝間を広くとると、当然隣のブドウ樹の陰に入らないので有効です。斜面も影が減るのでいいですね。
もう一つは水面の近くです!水面は太陽光を反射するので、その反射した光も吸収しよう!って事ですね。
これを全部行っているのが、ドイツのモーゼルです。川べりの断崖絶壁に畑をわざわざ築いているのは、段差と水面が欲しいからです!
光が多すぎる場合の被害
多すぎる場合は、ブドウその物に光が当たって、焼けたみたいな風味が出ちゃう被害があります。
それをしない為に、キャノピーマネージメントと言う作業が必要です。ブドウを葉っぱで隠してあげる作業ですね。
一番やりやすいのは株仕立て(ゴブレ)です。上に伸びて垂れさがるタイプですからね。日当たりが強い北ローヌとかスペインでゴブレが多いのはこの為です!
水による被害

植物ですからね。水が最大の問題です。
どんな時が問題って?当然ながら両極端な状況です。まずは足りない変からいきましょう。
水不足問題
最近、既存の産地で深刻な問題となりつつあるのがこの問題です。温暖化が進むと、もともと水がある所の水は増えて、ない所は減ると言われています。
ある所は想像しやすいのが我々日本人です。雨が増えてますよね・・・明らかに。これはこれで脅威なので、過剰問題で書きますね。
反対にない所は「さらになくなっている」ので深刻なんです。ワインの旧世界、つまりヨーロッパでも昔から地中海性気候がはっきりしてる所は、夏場の雨不足は言われていましたが、ヨーロッパルールで「灌漑禁止」と言うルールがあるので、灌漑をしていません。(特例地域は最近あります)
伝統的に灌漑していなかった地域は、要はしなくても何とかやってこれてたんですね。土の保水率がよかったり、ちょっとだけ雨が降ったりと、やりくりできてたのですが、ここ10年ぐらいは、南仏当たりの生産者は毎年のように「雨が降らなすぎる。このままじゃブドウが成長しない」なんて悩んでいます。
僕が扱うワインでも干ばつで収量が半減なんてのがここ数年本当にあります。
ニューワールドはもともと灌漑を頼りに、半分砂漠みたいなところで畑を築いてるパターンが非常に多いので、そう言ったニューワールドも深刻な問題になっています。
最近のニュースで見たのは2020年の「チリ・アコンカグア地方」の雨量が「過去最低だった2019年からさらに80%少ない。だから手も洗えない。コロナ禍なのし・・・」と言うニュースを見ました。去年更新した過去最低の1/5しかないって・・・手も洗えないんじゃ灌漑用水なんて確保できません。
基本的な解決方法は今までは灌漑でしたし、これからも灌漑しかありません。
なので一応灌漑の方法を解説します。
※灌漑とは水やりの事です。英語ではイリゲーション(irrigation)です。
・フルードイリゲーション
直訳すれば洪水灌漑。要するにどばーっと畑に水を撒く、田んぼみたいにする方法ですね。これは雨は降らないんだけど、実は水に困ってない地域の作戦です。
アルゼンチンとかでたまにやるみたいですよ。
・スプリンクラー
スプリンクラーです。はい。水まいてる感じですよね。
欠点はどうでもいい所にも水が飛ぶからもったいない!そして、全体が濡れちゃうので湿気る。そうするとカビ系の病気が繁殖する事です。
・ドリップイリゲーション(点滴灌漑)
最も主流だが、最も金がかかるシステムがこれです。
ブドウ畑にパイプを通して、その中を水が流れてい行くんですが、ブドウの樹の根元に水が垂れるように、パイプ穴をあけておくと、そこから水がポタポタ点滴のように垂れる、ピンポイント水やりですね。

こんな感じです。ポタポタ。
お水過剰問題
今度は水が多い場合の被害です。
まず第一に収穫直前に水が多い場合ですね。
これはよく聞くと思いますが、収穫直前に雨が降ると、その水をブドウの樹が一気に吸い上げるので、ブドウの実が水膨れしてしまう被害です。
ブドウの粒が水ででかくなると酷い時は「玉われ」しちゃいます。そうでなくても水で膨らむと、いろんな要素が薄まるわけですから、ワイン自体の味も大幅に低下してしまいます。
対処法は、お天気予報とにらめっこして、収穫時期を見極わめる!これしかありません。
「本当はあと2日収穫を待ちたいんだけど、明日から2日連続で雨予報」
こんな状況は生産者を思いっきり悩ませるわけです。「もうもう少し酸落ちてから収穫したいんだけど、でも雨降って水膨れしたら・・・えーん、どうしよー!」てなっちゃうわけです。
もう1つはワインブドウの生産地ではあまりないですが、水が多すぎて根腐れするパターンですね。
ワイン生産地は基本的に乾燥してる地域がほとんどですから、あまり実際に問題になる事はなさそうです。あるとすれば・・・「日本」ですね。今年(2020年)ぐらいの雨量になると・・・きついですよね。
その他の自然の驚異

「温度」「光」「水」に分類し辛かった問題をいくつか「その他」で解説します。
雹
雹による被害ですね。英語だと「Hail Storm」。
雹は氷の塊ですから、落ちてくるとブドウの実とか葉っぱに傷つけそうなのは、何となく想像つきますよね。
しかし世界の雹は我々日本人が思ってるのとスケールが違います。我々はせいぜいビービー弾ぐらいの氷が降ってくるのが雹だと思っていますが、世界の雹は

ご覧の通りでかいです!!ニュースでは「テニスボール大」って言うのも見た事があります。テニスボールが落ちてきたら、パラパラじゃなくてドスドス落ちてくる感じですよね。
テニスまで行かなくても、この写真ぐらいのでも、ブドウの樹その物が傷ついて、最悪の場合ブドウの樹が枯れます。ですから、深刻な脅威なわけです。
対処法は1つは確実で、もう1つは実験中ですが、まず確実な方
・ネットを張る
しょっちゅう雹が来るので有名なのはアルゼンチンです。この辺の人は雹が降る前提なので、あらかじめいつでも広げられるように、ブドウ畑に雹除け用のネットが設置されてたりします。
めっちゃ費用的には高いらしいですよ。
・天候を変える!!
こっちは実験中です。雹を降らせそうな積乱雲が出来たら、そこ目掛けてバズーカを放つ。そして積乱雲の中で炸裂した金属だったかな?それで積乱雲の成長を阻害する。みたいな方法です。ちょっと正確な情報が見つからずうろ覚え情報です。
まぁ、積乱雲を人工的に消してしまおうぜ!って言う作戦が考えられているって事だけ抑えてください。まだ実験段階です。
強風
極端な強風は当然ブドウ畑にも脅威です!垣根仕立ての場合、風向き次第では正面からもろに受けて、垣根が倒れるかもしれません。
温暖化の影響で起こる、天候の変化でこの風が問題になりつつあるのは南アフリカですね。「ケープドクター」と言う教科書的には「気温上昇を助けてくれる!」って書かれてる風が、最近強風化してきていて、「全然ドクターじゃねぇよ!デストロイヤーだよ」ぐらいな時が出てきてるそうです。
普通の風に対する対処法は風の方角って大体決まってるので、それに合わせて畑の向きを決めておく!とか低い仕立てにしておくとかです。
ギリシャのサントリーニ島は風強いの前提なので、最も特殊で、低くした上に巻きます!

こんなバスケット状にするわけですね。で、ブドウはこのかごの中で風から守られて生育していきます。斬新な事思いつきましたよね。
まとめ
ブドウ畑に起こりそうな自然災害は大体わかりましたかね?
地震は世界的にはほぼないのでカウントされていませんが、前に大き目な地震でがけ崩れしちゃった日本のブドウ畑の話は聞いた事があるので、脅威ではありますよね。
産地毎に襲ってきそうな災害は大体予見できるので、それに合わせて対策する物、対策しない物がありますが、その辺も生産者の判断次第です。
焚火の項でも言いましたが、金銭的に対策を諦める場合もありますし、自然の驚異に立ち向かって毎年違った1年を過ごすのは大変ですよね。